(1)とにかく簡易型スペアナとして安価に製作したい人
---->ダイオード検波回路
(2)簡易型ではあるが、そこそこ性能のあるスペアナとして製作したい人
---->反転型・半波整流検波回路
(3)本格的にスペアナを製作したく、性能面を重視したい人
---->全波整流検波回路
これまで解説してきた整流回路ですが、大きく分けて半波整流と全波整流回路があります。半波整流回路では、非反転型と反転型に分けられます。各種ある中で、スペアナの検波回路として使っていくためには、どの回路が一番良いか検討しましょう。
![]() あなたは、どのコース(検波回路)を選びますか?
あなたは、どのコース(検波回路)を選びますか?
(1)とにかく簡易型スペアナとして安価に製作したい人
---->ダイオード検波回路
(2)簡易型ではあるが、そこそこ性能のあるスペアナとして製作したい人
---->反転型・半波整流検波回路
(3)本格的にスペアナを製作したく、性能面を重視したい人
---->全波整流検波回路
![]() ダイオード検波回路
ダイオード検波回路
とにかく簡易型スペアナとして安価に製作したい人は、図1の回路のように、ダイオードD(順方向電圧の小さいゲルマニウム・ダイオードや、ショットキ・バリア型)を使用して半波整流します。この回路は、ダイオードの順方向電圧の影響を受けるため、入力電圧の振幅が小さいと誤差が大きくなります。検波出力をAD変換し、ソフトで出力値を補正する必要がありますが、数100MHz程度までの周波数も検波することが可能で、なんと言っても簡単なのがこの回路です。
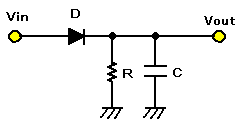 |
| 図1.ダイオード検波回路例 |
![]() 反転型・半波整流検波回路
反転型・半波整流検波回路
簡易型ではあるが、そこそこ性能のあるスペアナとして製作したい人にお勧めです。455kHzで歪を少なくするには、LM6361などの高速OPアンプが必要になってきます。図2に反転型・半波整流検波回路の例を示します。
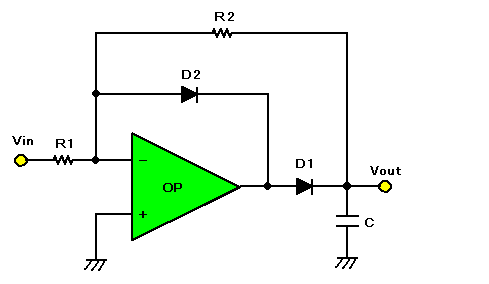 |
| 図2.反転型・半波整流検波回路 |
検波回路の負荷抵抗R(RはR2に相当)と平滑コンデンサCの値ですが、時定数τ=CRによって出力波形がどのように変化するか次に見てみましょう。使用したパーツは、OPアンプLM6361を用いて電源電圧±12Vで動作させました。また、ダイオードD1,D2は1N60を接続し、抵抗には一般の炭素皮膜抵抗で、R1=R2=10kΩを接続しました。ここで、負荷抵抗はR(=R2)=10kΩとなります。平滑用コンデンサは、C=0pF(無接続)、100pF、1000pFを、それぞれ付けた場合でデータを取りました。入力周波数は、f=455kHzです。
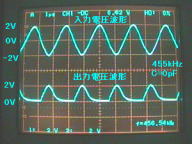 図3(a).反転型・半波整流検波回路
図3(a).反転型・半波整流検波回路
C=0pF(無接続)のときの
入力/出力波形
上段:入力波形(455kHz正弦波)
下段:出力波形(半波整流検波出力)
(縦軸:2V/div,横軸:1μs/div)
図3(a)は、C=0pF(無接続)のときです。出力電圧波形のピークの形状ですが、やや右側がなだらかに見えます。これは、基板の配線容量や、オシロスコープのプローブの容量が影響しているためと思われます。
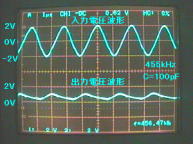 図3(b).反転型・半波整流検波回路
図3(b).反転型・半波整流検波回路
C=100pF接続のときの
入力/出力波形
上段:入力波形(455kHz正弦波)
下段:出力波形(半波整流検波出力)
(縦軸:2V/div,横軸:1μs/div)
図3(b)は、C=100pFを接続したものです。出力電圧波形のピークの形状がなだらかになり、波打っているように見えます(リップルという)。検波回路としては、まだ不十分ですので、もう少し容量を大きくする必要があります。時定数は、τ=CR=1[μs]です。
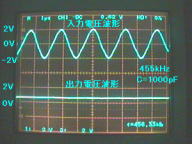 図3(c).反転型・半波整流検波回路
図3(c).反転型・半波整流検波回路
C=1000pF接続のときの
入力/出力波形
上段:入力波形(455kHz正弦波)
下段:出力波形(半波整流検波出力)
(縦軸:2V/div,横軸:1μs/div)
図3(c)は、C=1000pFを接続したものです。出力電圧波形のリップルが無くなり、検波回路として十分使用できる段階になりました。時定数は、τ=CR=10[μs]です。
![]() 全波整流検波回路
全波整流検波回路
本格的にスペアナを製作したく、性能面を重視したい人にお勧めです。455kHzで歪を少なくするには、LM6361などの高速OPアンプが必要になってくることと、精度を向上させるために高精度抵抗が必要になってきます。
図4に全波整流検波回路の例を示します。全波整流回路の解説ページで紹介したR3の経路ですが、時間遅れ要素は特に考慮しませんでした。スペアナの検波回路として、絶対値出力を平均化して直流化する場合はあまり問題とはなりません。
さて、ここでノウハウを一つご紹介します。平滑回路のコンデンサの接続ですが、CをOP2の出力と反転端子間に接続しています。OP2は、いわゆる積分回路となり、ローパスフィルタの役目を果たします。時定数はτ=R5・Cとなります。OP2アンプの出力インピ−ダンスが低いため、反転型・半波整流回路のようにCを出力端子とGND間に直接入れることはできません。もし、入れるとしたら、負荷抵抗Rを介してから接続するようにします。この例ではR5を負荷抵抗Rとみなすことで、1本でも抵抗の本数を削減しています。
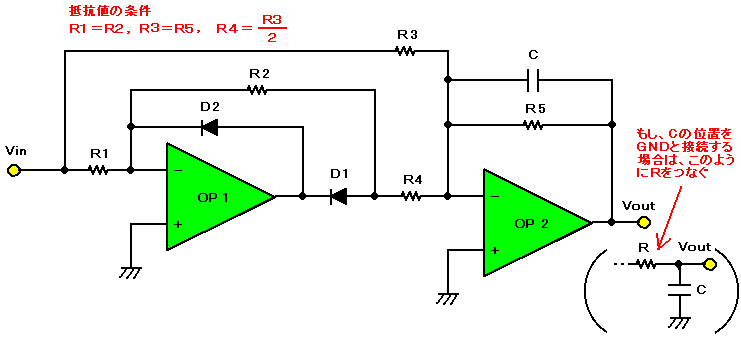 |
| 図4.全波整流検波回路 |
全波整流回路の抵抗は、金属被膜抵抗など高精度のものを必要とします。ここは迷わず集合抵抗を使います。集合抵抗は部品点数を減らすだけでなく、全波整流回路のように抵抗比が重要な回路に効果的です。例えば10kΩの集合抵抗では、R1=R2=R3=R5=10kΩ、R4は10kΩ抵抗×2個を並列接続して5kΩとします。図5の集合抵抗では4個の抵抗で構成されていますので、R1、R2の組合わせで1個使用し、R3、R5、R4のパラ接続の組合わせで集合抵抗を使うことになるでしょう。
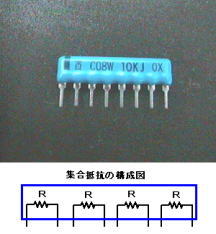
図5.集合抵抗の外観
抵抗値は10kΩ
4個入り
検波回路の時定数τ=CRによって出力波形がどのように変化するか次に見てみましょう。使用したパーツは、OPアンプLM6361を2個用いて電源電圧±12Vで動作させました。また、ダイオードD1,D2は1N60を接続し、抵抗には先程述べた10kΩ集合抵抗を接続しました。ここで、負荷抵抗はR(=R5)=10kΩとなります。平滑用コンデンサは、C=0pF(無接続)、100pF、1000pFを、それぞれ付けた場合でデータを取りました。入力周波数は、f=455kHzです。
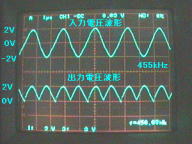 図6(a).全波整流検波回路
図6(a).全波整流検波回路
C=0pF(無接続)のときの
入力/出力波形
上段:入力波形(455kHz正弦波)
下段:出力波形(全波整流検波出力)
(縦軸:2V/div,横軸:1μs/div)
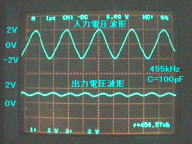 図6(b).全波整流検波回路
図6(b).全波整流検波回路
C=100pF接続のときの
入力/出力波形
上段:入力波形(455kHz正弦波)
下段:出力波形(全波整流検波出力)
(縦軸:2V/div,横軸:1μs/div)
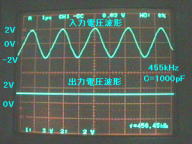 図6(c).全波整流検波回路
図6(c).全波整流検波回路
C=1000pF接続のときの
入力/出力波形
上段:入力波形(455kHz正弦波)
下段:出力波形(全波整流検波出力)
(縦軸:2V/div,横軸:1μs/div)
図6(c)は、C=1000pFを接続したものです。出力電圧波形のリップルが無くなり、検波回路として十分使用できる段階になりました。時定数は、τ=CR=10[μs]です。
![]() 時定数τ=CRについて
時定数τ=CRについて
ダイオード検波回路の負荷抵抗Rと平滑コンデンサCの値ですが、時定数τ=CRを大きくすると検波効率を上げることができます。ただし、あまり過大になりすぎると、放電に要する時定数が長くなってしまいます。そうすると掃引したときに、スペアナの信号ピーク波形に検波包絡線が追いつかなくなって歪を発生します。これをダイヤゴナル・クリッピング歪と呼んでいます。
図7は、検波回路の入出力特性を示したものです。入力Vinですが、中間周波数f=455kHzで、掃引により変調された山型のスペアナ・ピーク波形になっています。理想的には、Vinの包絡線に沿って検波されるのがよいのですが、時定数τ=CRが過大すぎると検波出力は赤色の線で示したように歪みます。
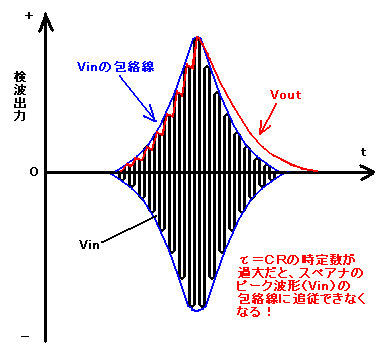 |
| 図7.検波回路の入出力特性 |
この歪を改善するためには、
![]()
となる式を満足するような、C,Rを使用しなければなりません。ここで、fmは掃引周波数に関係してきます。掃引周波数を速くするとCRの値を小さくしなくてはならず、検波効率は低下します。逆に、CRを大きくして検波効率を上げることを優先すれば、掃引周波数を遅くする必要があります。実験結果では、R=10kΩ、C=1000pF程度の容量で(τ=10[μs])、リップルは無視できるようです。
 |
|
 |